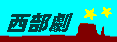
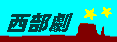
<2010年代の西部劇>制作年降順
荒野の誓い、 ゴールデン・リバー、 ある決闘 セントヘレナの掟、 マグニフィセント・セブン、 ジェーン、 レヴェナント 蘇えりし者、 ヘイトフル・エイト、 トマホーク ガンマンVS食人族、 荒野はつらいよ〜アリゾナより愛をこめて〜、 ローン・レンジャー、 ジャンゴ 繋がれざる者、 宿敵 因縁のハットフィールド&マッコイ、 ブラックソーン ブッチ・キャシディ 最後の決闘、 トゥルー・グリッド
荒野の誓い HOSTILES
2019年 アメリカ 135分
監督・脚本・製作:スコット・クーパー
出演:ジョー・ブロッカー大尉(クリスチャン・ベール)、ロザリー(ロザムンド・パイク)、
トーマス・メッツ曹長(ロリー・コクレイン)、ヘンリー・ウッドソン伍長(ジョナサン・メジャース)、キダー中尉(ジェシー・プレモンス)、デジャルダン上等兵(ティモシー・シャラメ)、チャールズ・ウィルス軍曹(ベン・フォスター)
イエローホーク(ウェス・ステューディ)、ブラック・ホーク(アダム・ビーチ)、エルク・ウーマン(クオリアンカ・キルヒャー)、リビング・ウーマン(タナヤ・ビーティ)、リトル・ベア(ザビエル・ホースチーフ)
試写で見る。
1892年、アメリカ西部。
インディアンとの戦いで武勲を挙げた騎兵隊大尉ジョー・ブロッカーは、刑務所の看守長をしていたが、ある日、服役中のシャイアン族の長イエローホークとその家族をモンタナ州の居留地まで送り届けるよう命じられる。かつての敵を護送する任務に乗り気でなかったジョーだが、旅の途中でコマンチ族の激しい襲撃を受け、彼らと手を組まざるを得ない状況に置かれていく。
旅の最初の方で、一行は、コマンチ族に夫と子どもを殺され、家と牧場を失くした女性ロザリーを保護する。彼女はあまりの悲劇に放心状態にあった。
カスター将軍率いる第七騎兵隊の全滅からウッデンド・二―のインディアンの虐殺など、先住民と白人の移民との戦いで、アメリカ西部において憎しみの連鎖が続いていた時代の話だ。インディアンは、昔なつかしい西部劇全盛時代には悪役として描かれ、ベトナム戦争後、インディアンに対する問題が取りざたされると西部劇の敵は他に移り、最近では、ガンマンがモンスター相手に戦う西部劇も珍しくない。というのが、一般的な見方だが、オールド・ウエスタンのころから、インディアンは白人の敵ばかりではなく、西部の地の案内役や相棒として登場する。インディアンは多種多様な種族に分かれ攻撃的な部族もあれば穏健な部族もあり、近くに住んでいる者同士には交流も生まれる。ほんの一部の例を言えば、「ローン・レンジャー」の相棒トントはインディアンだし、姪をさらったコマンチを憎む「捜索者」のイーサン(ジョン・ウェイン)の若い相棒マーティン(ジェフリー・ハンター)はインディアンと白人のハーフである。そうした複雑な事情を抱え、昨今の西部劇というか、西部を舞台とするドラマは、インディアンを腫れもののように扱うか(「先住民族」という、何も特定しない言葉が出てきたのもその流れだ)、そうした話題を避けてきたように思う。が、この映画はまっこうからその問題に取り組んでいて、ぶれない。
ロザリーを襲ったのはコマンチで、イエローホークらはシャイアンである。彼の妻エルク・ウーマンはなにかとロザリーを気づかい、ロザリーも少しずつショックから立ち直って心を開いていく。
が、男たちの恨みは大きい。ジョーは、イエローホークとの戦いで多くの友人を失った。騎兵隊の兵士たちもそれぞれに心の傷を抱えている。イエローホークらにとっては戦いをしかけてきたのは白人の方であり、彼らは自分たちの土地を守るために戦い、多くの同胞を失い、刑務所に収監されるという憂き目に遭いながらも、常に超然としている。
やがて、共通の敵を前に、対立していた男たちは協働していく。が、そう聞いて期待するような爽快感はない。ジョーは、恨み言を繰りながらもイエローホークに和解を申し出て、ついにその手を取って握手さえするが、彼の顔に笑みはない。また、イエローホークの方は終始一貫した態度で、ジョーの気持ちがどうであれあまり関係ない様子である。
監督は、安易に楽観しない。物語はハードに暗い方へと向かっていく。配給側がウエスタン・ノワール第3弾と銘打っているように、トーンは終始陰鬱である。
最後は希望を持たせて終わるというが、ほんとうにあれが希望なのか。新しい人生を求めてロザリーだけがシカゴへ旅立ち、ジョーとリトル・ベアは西部に残り、二人でこれからの西部を生きる方がよかったとわたしは思う。
一行の旅は、ニューメキシコから、コロラド、ワイオミングを経てモンタナへ。森での夜のキャンプ・シーンも多く、西部の景色を楽しめたのがよかった。(2019.9)
ゴールデン・リバー THE SISTERS BROTHERS
2018年 フランス・スペイン・ルーマニア・ベルギー・アメリカ 120分
監督:ジャック・オーディアール
原作:パトリック・デウィット「シスターズ・ブラザーズ」
出演:イーライ・シスターズ(ジョン・C・ライリー)、チャーリー・シスターズ(ホアキン・フェニックス)、ジョン・モリス(ジェイク・ギレンホール)、ハーマン・カーミット・ウォーム(リズ・アーメッド)、メイフィールド(レベッカ・ルート)、提督(ルトガー・ハウアー)、ミセス・シスターズ(キャロル・ケイン)
1851年、アメリカ。
「提督」と呼ばれるボスの命令で、殺し屋兄弟シスターズ・ブラザースのチャーリーとイーライは、ハーマン・カーミット・ウォームという名の男を追うことに。弟のチャーリーは人を殺すことにためらいがない危険な男だが、兄のイーライは温厚で殺し屋稼業から足を洗いたいと思っている。
二人は、オレゴンからアメリカ大陸を横断して、ゴールドラッシュに沸くカリフォルニアを目指す。その間、チャーリーは飲んだくれ、イーライは毒クモに刺されたり、馬が熊に襲われたりと災難続き。女ボス、メイフィールドが牛耳る町では、彼女の手下に襲われるが、返り討ちにする。イーライは見事な銃撃をして見せ、実はかなりの銃の使い手であることを示す。
兄弟は、やっとたどり着いたサンフランシスコで、「提督」が放った連絡係モリスに会おうとするが、モリスは提督を裏切ってウォームとともに金を採りに行ってしまった後だった。二人を追う兄弟も、科学者を自称するウォームの発明した、金をたちどころに見つけられる秘薬の存在を知り、仲間に加わる。4人は力を合わせて金を手に入れるが、劇薬はウォームとモリスの命を奪い、チャーリーも右腕を失う。(邦題の「ゴールデン・リバー」は、秘薬によって夜の川底に浮かび上がる、きらきら光る金を指す。)
兄弟は、提督との対決を決心し、オレゴンの屋敷に向かうが、そこでは提督の葬式が営まれているのだった。対決をする必要もなくなり、兄弟は、母の住む故郷に帰る。
原作の西部小説は、大衆娯楽小説的なテーマを扱いながらも、オフビートな中にそこはかとなく文学臭さの漂う作品だったが、映画の方も、西部劇でありながら、活劇というよりは、人間ドラマとしてスマートに決まっている。
シスターズ・ブラザースという名前からして人を喰った感じだが、邦題よりはこちらの方が好きだ。チャーリーの暴力性をさんざん見せながら、じつはイーライの方が凄腕ガンマンだったり、ウォームがモリスにユートピアのような町をつくりたいという夢を語ったり、やっとウォームを見つけたと思ったら兄弟二人して仲間に加わったり、うまくいったと思ったらことのほか悲惨な結果になったり、いざ提督と対決と乗り込んだら提督はすでに死んでいたり、そして、ラストは二人して親孝行なことに故郷の家に帰ったりと、展開は右かと思えば左、左かと思えば右と、はぐらかしの連続である。気が利いているといえば気が利いているのかもしれないが、あざといと言えばあざといような気もする。でも、こうゆうのが好きな人は好きだろう。
わたしは、このはぐらかし戦法は特にいいとも悪いとも思わないが、最後に実家に戻って、兄弟の母のシスターズ夫人が出てくるのはよかったと思う。
小説ほど軽妙洒脱ではなく、地に足のついた映画という感じ、なによりイーライ始め4人の男たちに好感が持てたのはうれしかった。
銃声がすごい、迫力があるという評価があるようで、たしかにすごい音だが、わたしはどうも花火のように聞こえてしまってしっくりこなかった。(2019.8)
<映画と原作小説の違い>
原作を読んだのは何年か前なので、細部は忘れてしまったが、覚えている範囲内で、映画と原作の違いをあげる。
・原作では、破壊的なチャーリーは兄、温厚なイーライは弟と、映画と逆になっている。(映画がなぜ兄とを弟を逆の設定にしたか定かではないが、あまり年齢序列にこだわらないアメリカでは、キャストの顔に合わせて変えたのかもしれない。)
・小説では、イーライは虫歯がひどくなって顔が腫れる。診てもらった歯医者に歯ブラシを勧められる。そのあと、クモに足を刺される。映画では、寝ている間にクモが口の中に入って顔が腫れる。
・小説では、メイフィールドは男で、兄弟にコテンパンにやられるが殺されることはなく、負けてすっからかんになった後でも今後について取引を持ちかけるという商魂たくましい様子を見せる。映画ではこわもての女ボスだが、兄弟に殺されてしまう。
・映画で、イーライが町のぬかるんだ道に渡した板の上を歩くが、小説では、知り合った女性といい感じになっていっしょにぬかるみの板を渡って歩くちょっとロマンチックなシーンになっている。
・小説では、最後は提督と対決する。このとき、イーライは、普段は温厚だが、一度切れたらチャーリーよりも手に負えなくなるという危険な一面を見せる。映画では、提督との対決は肩透かしに終わる。
ある決闘 セントヘレナの掟 THE DUEL 元のタイトル:BY WAY OF HELENA
2016年 アメリカ 110分
監督:キーラン・ダーシー=スミス
出演:エイブラハム・ブラント(ウディ・ハレルソン)、デヴィッド・キングストン(リアム・ヘムズワース)、マリソル(アリシー・ブラガ)、アイザック(エモリー・コーエン)、ナオミ(フェリシティ・プライス)、ロス知事(ウィリアム・サドラー)、モリス医師(ラファエル・スバージ)、マリア(キンバリー・ヒダルゴ)、カルデロン将軍(ホセ・ズニーガ)
「悪党に粛清を」に続くウェスタン・ノワール第二弾とか、「地獄の黙示録」西部版と聞いて、またも暗い西部劇かと思いつつも、せっかくの新作なので見に行った。
1886年、メキシコとアメリカの国境を流れるリオ・グランデ川に連日メキシコ人の遺体が流れ着く。州知事は、テキサス・レンジャーのデヴィッドに、上流の町マウント・ハーモンへの潜入捜査を命じる。町の有力者である説教師のエイブラハム・ブラントは、南北戦争中に名を知られた南軍兵士であったが、デヴィッドとはさらに深い因縁のある男だった。幼少のころ、ヘレナという町で、諍いからブラントに決闘を挑んだ父が彼に敗れて死んだのだった。その決闘はヘレナ式と呼ばれ、お互いの左手を縛った状態で小ぶりのナイフで攻撃するという過酷なものだった。(西部史に詳しい都築哲児氏によれば、これは実際にヘレナという町でこういう形式の決闘があったという記録が残っているらしい。)
デヴィッドは、いっしょに行きたいと言い張るメキシコ人の妻マリソルを伴ってマウント・ハーモンを訪れ、ブラントの勧めで新任保安官となる。説教師であるとともに資産家であるブラントは町に君臨していた。彼は美人のマリソルが気に入り、信仰を説いて彼女を取り込もうとする。町は閉鎖的で自ら訪れる旅行者はめったにいなかったが、ブラントが呼ぶ「客」は頻繁にやってきた。密偵を続けるデヴィッドは、ブラントとその一味が行っている残忍な「商売」を目撃する。
白い衣装に身をつつんだスキンヘッドのハレルソンが、派手で怖い説教師を不気味に演じて逆に爽快な感じさえする。対するヘムズワースも食われる主役に甘んじてはいない。腕の立つガンマンで、復讐心のみに捕らわれずブラントに対するのがよい。
ブラントの息子アイザックは、大物を父親にもつバカ息子で、かつての西部劇にもよく見られた役回り。だめな奴だが、父に認めてもらおうと悲壮な決意をしてデヴィッドにヘレナ式決闘を挑むものの、やはりあっさり敗れてしまって、ちょっと憐れを誘う。
最後の岩場でのデヴィッドとブラントの撃ち合いはたいへん見応えがある。血がやたら出るし、ブラントの動きに気づかないデヴィッドはいささか間抜け、それを女性に助けられるというのも定番すぎてなんだかなという感じだが、最近はとにかく多勢に無勢、敵が多けりゃ多いほど盛り上がるだろうといった設定のものが多くて(「マグニフィセント・セブン」(後出)も「グレート・ウォール」も然り)ちょっとうんざりしていたので、1対1の対決を丁寧に描いてくれたのが、よかった。(2017.6)
マグニフィセント・セブン The Magnificent Seven
2016年 アメリカ 133分
監督:アントワー・フークア
出演:サム・チザム(賞金稼ぎ。デンゼル・ワシントン)、ジョシュ・ファラデー(ギャンブラー。クリス・プラット)、ヴァスケス(流れ者。マヌエル・ガルシア=ルルフォ)、グッドナイト・ロビショー(スナイパー。イーサン・ホーク)、ビリー・ロックス(暗殺者。イ・ビョンホン)、ジャック・ホーン(ハンター。ビンセント・ドノフリオ)、レッドハーベスト(戦士。マーティン・センスマイヤー)、
エマ(ヘイリー・ベネット)、テディ・Q(ルーク・グライムス)、バーソロミュー・ボーグ(ピーター・サースガード)
※7人のガンマンの俳優名の前にあるのは、宣伝チラシなどに載っていた肩書きだが、ちょっとずれてるかもと思う部分もなきにしもあらず。
1879年、アメリカ、ローズ・クリークの町。
金鉱会社を経営する実業家のボーグは、事業の邪魔になる開拓民たちを町から追い出そうとして無茶な立ち退きを提案し、さらに用心棒のガンマンたちを使って教会に火をつけ、反発した住民を撃ち殺すという暴挙に出る。夫を殺されたエマは、開拓民仲間のテディQとともに、ボーグに対抗するため、すご腕のガンマンを探す旅に出る。
州をまたぐ犯罪取り締まりの委任執行官サム・チザムの仕事ぶりを見たエマは、サムに話をもちかける。サムはボーグを倒す仕事を引き受け、一緒に行く仲間を集め始める。酒好きで女好きのアイリッシュのギャンブラーでニ丁拳銃のファラデー、お尋ね者のメキシコ人ヴァスケス、元南軍の狙撃手で南北戦争の英雄だったグッドナイトと、彼に付き従う東洋人の若きナイフ使いビリー、巨漢の猟師ジャック、はぐれアパッチの若者レッドハーベストらが集まる。
言わずと知れた、「七人の侍」(1954年)の西部劇版リメイク「荒野の七人」(1960年)のさらなるリメイクである。
「マグニフィセント」って一体何だと思った人は多いだろうが、「壮麗な」という意味の形容詞である。中学生のころ、「荒野の七人」の原題を調べた際に初めて知ったが、後にも先にもそこでしか見たことがない英単語である。この邦題は直訳ですらない、原題のカタカナ読みなのである。
「荒野の七人」は、昔、テレビで見て以来、とても好きな映画だ。(なぜか「流しの公務員の冒険」という本の感想でも書いたのだが、)私は子どものころテレビの洋画劇場で映画を見て育った世代である。当時、テレビでは毎晩何かしらの洋画をやっていて、西部劇も多かった。中でも、「荒野の七人」はたいそう盛り上がったものの一つである。そして、気持ちが高揚しているところに、親からオリジナルの「七人の侍」がいかに優れた映画であるか、それに比べたら「荒野の七人」はだめだめだということを言われ、せっかくの気分を台無しにされるという辛い思いをしたものだが、同じ経験をした同年代の人は少なからずいるのではないだろうか。「七人の侍」は確かに素晴らしい映画だと思うが、「荒野の七人」は、7人それぞれにしっかりとした個性と魅力があり、特に侍たちには見ることのなかった合理的で俗物的で憎めない男ハリー(ブラッド・デクスター)が7人の中に含まれている点がアメリカ映画ならでは、敵の山賊カルベラ(イーライ・ウォラック)にも彼なりの男気があるのが往年の西部劇の悪役ならでは、さらに広大でからっとした西部の自然を反映した軽快さ・明るさなどもあって、いろいろ行き届いたよい映画だと私は思っている。
さて、56年の歳月を経てのリメイクである。7人は、オリジナルの面々に必ずしも一致はしない。リーダーは黒人、ナイフ投げは韓国人、そして最後に加わるのは弓矢の名手のインディアンと、人種のるつぼアメリカを前面に出した人物設定である。が、しかし、それでおもしろくなっているかというとこれが特にそういう様子でもないのである。たしかに、クリス・プラット演じるファラデーは、昨今希少な陽気で頼りになる西部男、個人的には久方ぶりのどストライクのキャラクターで大いに魅了された。また、狙撃手としてのトラウマにさいなまれるグッドナイトと彼を慕うビリーの2人組もなかなかよかった。世間的にはエマが好評のようで、夫を殺された不幸な未亡人から銃を手にして毅然とした女になっていく様子もなかなかよい。が、ヴァスケスやジャックやレッドハーベストについてはもっと人となりを見たかったし、町の人とのやりとりももっとちゃんと描いてほしかったし、なによりチザムについては、最後のネタばらしによって彼が何を思ってここまできたのか判断がつかなくなって戸惑う。また、ボーグが山賊でなく実業家なのもだいぶ残念である。ということで、物足りないところはある。
銃撃戦はかなり気合が入っていた。また、7人それぞれの銃や武器の扱い方がバラエティに富んでいて、おもしろい。(ちなみにファラデーのニ丁の銃の挿し方は、右側が通常の抜き方で抜ける向き、左側は逆向きになっているが、これはまず右手で右の銃を抜いて撃ち、弾がなくなったら左側の銃を右手で抜いて使うためだそうです。byトルネード吉田。)しかし、敵の数を増やせばいいというものではない(同様のことは「十三人の刺客」のリメイク版でも「ジェーン」でも思った)。多すぎる敵に対しては予め爆弾をしかけておいて出鼻にできるだけ大勢倒すという方法くらいしかない(「ジェーン」でもやっていた)。それと、ボーグが「あれを出せ。」と言うのを聞いたときも、それまでなんの前振りもなかったが、まさかまたあれかと思ったら、やっぱりガトリング銃だった。「続・荒野の用心棒」での初登場の際はかなり強烈な存在感を放っていたが、昨今はあちこちで見かけすぎて、もういいよという感じだ。(「ジャンゴ 繋がれざる者」で出さなかったタランティーノはさすがである。)敵の顔が見える適度な人数による銃の撃ちあいが西部劇の味ではないかと思うのだ。
最後の最後でなつかしいテーマ曲が流れたのはうれしかった。ここで来るかという感じ。1人1人の顔が順々に映し出されるクレジットも、よかった。(2017.1)
ジェーン JANE GOT A GUN
2016年 アメリカ 98分
監督:ギャヴィン・オコナー
出演:ジェーン・ハモンド(ナタリー・ポートマン)、ダン・フロスト(ジョエル・エドガートン)、ビル・ハモンド(ノア・エメリッヒ)、ジョン・ビショップ(ユアン・マクレガー)、ヴィック・ビショップ(ボイド・ホルブルック)、フィッチャム(ロドリゴ・サントロ)、メアリ(パイパー・シート)
★あらすじバラしています★
1871年のアメリカ西部を舞台にしたナタリー・ポートマン主演の西部劇。
ジェーンは、幼い娘と夫のハム(ハモンド)とともに暮らしていたが、ある日、ハムは銃撃を受け瀕死の重傷を負って帰宅する。ハムは、かつてのボス、一帯を牛耳るジョン・ビショップの手下たちと争いになり、相手を倒したものの自分も撃たれてしまったのだ。仲間を殺されたビショップは、追っ手を差し向けてくる。ジェーンは、娘を知人宅に預け、南北戦争の英雄で元恋人のダン・フロストに助けを求める。ダンは、最初は彼女をつけ放すが、やがて手を貸すこととなる。ジェーンとダンとハムは、荒野の真ん中に立つ家で、ビショップ一味を迎え撃つ。
愛する夫と娘を守るため、ヒロインは銃をとった、という謳い文句となっている。が、娘の出番はほとんどなく、家族ものというよりは、一人の女と二人の男の恋愛ドラマといった感じである。
ジェーンは婚約者だったダンの子を身ごもっていたが、ダンは南北戦争に出征して終戦後3年が過ぎても戻ってこなかった。彼は死んだものと思ったジェーンは、幼い娘を連れ、新天地を目指して西部に向かうが、旅の途中でビショップの世話になったことから、彼に目をつけられる。娼館に追いやられるところを、彼女を好きになったハムによって救出される。が、娘はビショップの手下の不注意から川で溺れ死んだと知らされる。ハムとジェーンはビショップ一味から逃げ、荒野に家を建てて暮らし始め、やがて2人の間に娘のメアリが生まれた。一方、南軍の捕虜になっていたダンはそんな事情も知らず、自分を裏切ったジェーンを恨んでいたのだった。
3人の男女の関係が丁寧に描かれている。通常の西部劇であれば、ハムかダンが主役となるところを、ジェーンが主役になっているため、女性目線なのが興味深い。負傷する夫を守るため、昔の恋人(嫌いになって別れたのでなく、好き合っているのに離れ離れになってしまったというのが大事)とともに戦う、大変な状況ではあるが、ある意味女冥利につきる話だとも言える。ジェーンだけでなく、ダンの側からの描写もけっこうあって演じるエドガートンがなかなかいいのだが、ハムについてはほぼジェーンの説明だけにとどまっているので彼自身が語るのをもっと聞きたかった気がする。
ビショップらを迎え撃つ直前の夕暮れ、家の前でジェーンとダンが話をする。いいシーンなのに、画面が暗すぎると思って見ていたら、クライマックスの銃撃戦は夜なのでさらに暗かった。
ダンのしかけた爆弾が爆発し、多くの敵を一気にやっつける際に炎が燃え上がり、生き残った敵との銃撃戦では、家の壁のふし穴ごしに銃撃の火花が散るのが闇の中に浮かび上がる。それはそれで見せるのだが、ほぼ音と炎で表される銃撃戦の様子は観念的というか、私としてはあまりしっくりこなかった。ビショップが家の中に入ってきてからのやりとりも、いたって凡庸である。
最後はめでたしめでたし。でも、もうちょっとなんかほしかったという思いは残る。(2016.10)
トマホーク ガンマンVS食人族 BONE TOMAHAWK
2015年 アメリカ 132分
監督・脚本:S・クレイグ・ザラー
出演:ハント保安官(カート・ラッセル)、チコリー保安官補(リチャード・ジェンキンス)、アーサー(パトリック・ウィルソン)、ブルーダー(マシュー・フォックス)、サマンサ(リリー・シモンズ)、ニック(エヴァン・ジョニカイト)、パーヴィス(デビッド・アークェット)、教授(ザーン・マクラーノン)、ウォーリントン氏(マイケル・パレ)、ポーター町長夫人(ショーン・ヤング)
ザラーに興味を持った家人が借りたDVDを見る。
はちゃめちゃなB級ウェスタンを思わせるタイトルとは裏腹に、渋くてハードで静かなホラー西部劇である。
岩山の奥深くに住む穴居人が、墓を荒らした無法者を追って密かに町にやってくる。町の保安官ハントは、負傷した無法者パーヴィスの手当てをしてもらうため、カウボーイのアーサーの妻サマンサを呼ぶ。アーサーは足を負傷し自宅で療養していた。パーヴィスとサマンサと保安官助手の若者ニックが事務所で一晩過ごすが、翌朝3人の姿が消えていて、近くの厩では惨殺された黒人の馬番の死体が発見される。「教授」と呼ばれる賢者のインディアンにより、山奥に住む謎の食人族に連れ去られたことが判明する。ハントと保安官補のチコリー、ガンマンのブルーダー、そして足を負傷したアーサーが、救出のため、現地のインディアンから禁断の場所とされている、穴居人の住む山奥へ向かう。
前半は、追跡隊の4人の男たちの旅の様子が静かに淡々と描かれる。ここで4人の人柄や人間関係が説明される。アーサーの足のケガは悪化し、彼は軍医だったチコリーの手当てを受けた後、岩山の麓に一人残って待つことになる。風の音のような、狼の遠吠えのような音が穴居人たちの合図でことがわかり、音が聞こえるとぞくぞくしてくる。
山奥へ入ってからは、追跡隊のあまりの不利さと穴居人たちのあまりの非道さによって、捕虜となっていたサマンサたちも捕まったハントらもこれはもう助かりようがないだろうと思わせる絶望的な状況に追い込まれていく。麓に残ったアーサーがなんとかできるとはとても思えなかったのだが、サマンサへの愛ゆえか、彼は超人的な力を発揮して救援に駆けつけるのだった。
渋い色調の画面に、物静かな人々、重低音の銃声、殺し合いによる容赦ない流血といった、最近のウエスタン風のつくりとなっている。西部の開けた風景と乾いた空気がいい。
3人が生き残ってひとまずよかったのだが、これから町まで帰るのがまた一苦労だなと思わずにいられない、切ないラストだった。(2020.10)
ヘイトフル・エイト THE HATEFUL EIGHT
2015年 アメリカ 168分
監督・脚本:クエンティン・タランティーノ
音楽:エンニオ・モリコーネ
出演:マーキス・ウォーレス少佐(サミュエル・L・ジャクソン)、ジョン・ルース/首吊り人(カート・ラッセル)、デイジー・ドメルグ(ジェニファー・ジェイソン・リー)、クリス・マニックス(ウォルトン・ゴギンズ)、ボブ(デミアン・ビチル)、オズワルド・モブレー(ティム・ロス)、ジョー・ゲージ(マイケル・マドセン)、サンディ・スミザーズ将軍(ブルース・ダーン)、OB(ジェームズ・パークス)、ジョディ(チャンニグ・テイタム)
ミニー・ミンク(ダナ・グーリエ)、シックス・ホース・ジュディ(ゾーイ・ベル)、エド(リー・ホースリー)、スウィート・デイヴ(ジーン・ジョーンズ)、チャーリー(キース・ジェファーソン)、ジェマ(べリンダ・オウィノ)、チェスター・チャールズ・スミザーズ(クレイグ・スターク)
ナレーター(クエンティン・タランティーノ)
★ネタバレあり!!★
タランティーノ監督によるミステリ仕立ての密室西部劇。
アメリカ、南北戦争後のワイオミング。レッドロックに向かう駅馬車が、吹雪のため、荒野の中にぽつんと立つロッジ(ミニーの紳士洋品店)に立ち寄る。馬車の乗客とロッジの先客、いわくありげな男女8人が、ともに一夜を過ごすことになったのだが・・・という話である。
駅馬車に乗っていたのは、賞金稼ぎのルース、彼に連行されている賞金首の女犯罪者ドメルグ、途中から乗車した元北軍の賞金稼ぎウォーレス、やはり途中乗車の自称レッドロックの新任保安官マニックス、御者のOB。ロッジにいたのは、ミニーに頼まれて店を預かっているというメキシコ人のボブ、死刑執行人のモブレー、カウボーイのゲージ、元南軍のスミザーズ将軍らである。数えると9人になるが、どうやらOBはごくまっとうな人で「ヘイトフル」ではないらしく、人数に含まれないようである。
いつもロッジにいる女店主ミニーの姿はなく、彼女が面倒を見ている車いすの男デイブの姿もない。ボブの説明に不審を抱いたルースは、ロッジにいる男たちの誰かがドメルグの仲間で彼女を絞首刑から救うために奪還しに来たのではないかと疑う。やがて、何者かがコーヒーに毒を入れ、殺人事件が発生、ロッジは、銃撃と血にまみれた修羅場と化す。
70ミリのフィルムで撮影されたにも関わらず、ほぼ密室劇である。駅馬車が行くワイオミングの雪景色は美しいが、最初の方しか出てこない。駅馬車内でも、ロッジでも延々とおしゃべりが続き、人物紹介がなされる。(駅馬車内と中継所での人間模様という意味ではジョン・フォードの「駅馬車」(1939年)と同様の素材のはずだが、タランティーノがやるとこうなるのかということで、激しく違うものになるのだった。)
この会話を退屈と感じるかどうかと、最後の修羅場をどう思うかで、映画の評価が分かれるかと思う。私は3時間と聞いて見に行くのを躊躇したのだが、見始めたら面白かった。
ウォーレスが「リンカーンの手紙」を持っているのはよかった。(文脈からわかると思うが、「メアリー・トッドが呼んでいる。床につく時間だ。」の「メアリー・トッド」はリンカーンの奥さんである。)
ルースが、疑心暗鬼となり、ロッジにいる男たち一人一人と話をするところでは、吹雪の中のテストという状況設定もあって、「遊星からの物体X」(1982年)で、カート・ラッセル演じる隊員が南極基地でやった「血液検査」を思い出した。
コーヒーに毒が盛られていることが分かってから、ギターを弾くドメルグとその向こうでコーヒーを飲もうとする人間が、いちいち律儀にピン送りされて撮られているのが、面白かった。
ジョディがいきなり床下から飛び出たのにはびっくりした。こうした登場からしても、最後の殺戮は、撃たれて血が出て、みんな死んで・・・と惨劇として受け止めるより、タランティーノのいつものクライマックスのお祭りだと思ってみた方が気が楽である。血もあれだけ出ると作り物めいて見える。毒だとは思うし、こんなもの見たくないという気持ちもわかるが、至って健全というか、ストレートな毒だと私は思った。
「キル・ビル2」でも感じたことだが、時間が戻って殺戮前の場面になるところがある。本作では、ルースらが到着する前に、ロッジで何があったのかが、時間を遡って示される。もう、観る者はみんな何があったか察しがついている。これから惨劇が起こることを予め知っていて、そのシーンを待つ、このはらはらドキドキ感はなかなかよい。(2016.3)
荒野はつらいよ アリゾナより愛をこめて A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST
2014年 アメリカ 116分
監督:セス・マクファーレン
出演:アルバート・スターク(セス・マクファーレン)、アナ(シャーリーズ・セロン)、クリンチ(リーアム・ニーソン)、ルイーズ(アマンダ・セイフライド)、エドワード(ジョヴァンニ・リビシ)、フォイ(ニール・パトリック・ハリス)、ルース(サラ・シルヴァーマン)、ルイス(エヴァン・ジョーンズ)、ジョージ・スターク(アルバートの父。クリストファー・ヘイゲン)、コーチーズ(ウェス・studiスタディ)、リンカーン(ギルバート・ゴッドフリート)、ドク(クリストファー・ロイド)、ジャンゴ(ジェイミー・フォックス)、カウボーイ(ユアン・マクレガー)
かわいい見かけとは裏腹な過激なギャグで人気を博したそうな熊のぬいぐるみが主人公の映画「テッド」で知られるセス・マクファーレン監督・主演の西部劇コメディ。(「テッド」は観ていません。)
原題は直訳すると「西部における百万の死にざま」となり、邦題より断然こっちの方が格好いい。そしてこのタイトルの通り、主人公の気弱な羊飼いの青年アルバートは、西部開拓時代のアメリカがどんなにひどいところか、人の死に方は百万通りもあり、生き延びるのは本当に大変だ、西部はつらいよ、とその時代の人間とは思えぬ価値観でもって、おのれの生まれついた時代を呪い、ぼやき続ける。
下ネタとエロ・グロ場面満載という評判や「こんな汚い映画初めて見た」という知人のジェントルマンの感想を耳にしていたので、どれだけ見るに堪えないものが出てくるのかと腹を括って劇場に行ったのだが、さほどじゃなかったというか、肩すかしというか、これよりもっとえげつないものが出てくる映画は過去にいくらでもあったし、この程度で引いちゃだめだ、そんなにお上品になるな、日本人、と思った。(でも、ママ友や娘とは見に行かないけど。)
マカロニ・ウエスタンが、60年代くらいまでの古き良きアメリカ正統派西部劇に対する暴力的なアンチテーゼだとすれば、これは、下ネタと軽口による比較的平和的なアンチテーゼというか。
オープニングは、シネスコでモニュメント・ヴァレーの景観を延々と楽しめ、クレジットのロゴもレトロ調だった(できれば、モニュメント・ヴァレーは空撮でなく、地上から撮ってほしかったが)。酒場のシーンの殴り合いは迫力があるし、パーティでみんながカントリーダンスをするシーンは楽しかった。他にも銃の手ほどきや馬ならぬ羊の群れに紛れての逃走など、西部劇でよく目にするような場面が多く見られ、下ネタやおちゃらけの部分もあるけど、基本的には、しっかり撮られていたと思う。
私の勝手な憶測だが、マクファーレンは、きっと西部劇が好きだ。だけど、正義のヒーローが悪い奴らをやっつける、まっストレートな西部劇をいまどき撮るのはちょっとなあというすかした現代感覚とかっこいいヒーローは柄じゃないという思いから、下ネタやアイロニーで煙に巻くという戦法に出たのじゃないだろうか。
不満なのは、うん○やエログロではなく、ちゃんとした撃ち合いシーンがないことだ。アルバートは平和主義で気弱な羊飼いなので、多少銃を扱えるようになっても、基本的には戦いを避けて逃げる。最後の決闘も凶悪なアウトローに勝つため、いろいろ工夫を凝らした展開となり、真っ向勝負とはいかない。銃を撃ちたがらない主人公は、それはそれで筋を通しているとも言えるが、西部劇ファンとしてはやはりそんなにすっきりはしない。
リーアム・二―ソンがよかった。彼が演じる西部の極悪ガンマンを見られてうれしかった。しかも、お尻を出して失神し、デイジーの花まで添えられる。あっぱれな役者ばかぶりにじんときた。
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「ジャンゴ」(本ページ後出)など他の映画のパロディも楽しかった。
このひと言(No.64.)「祭りでは、人が死ぬ。」“People die at the fair.”
ローン・レンジャー THE LONE RANGER
2013年 アメリカ 149分
監督:ゴア・ヴァービンスキー
出演:トント(ジョニー・デップ)、ジョン・リード/ローン・レンジャー(アーミー・ハマー)、レベッカ・リード(ルース・ウィルソン)、ダン・リード(ジェームズ・バッジ・デール)、ダニー・リード(ブライアント・プリンス)、レイサム・コール(トム・ウィルキンソン)、ブッチ・キャベンディッシュ(ウィリアム・フィクトナー)、フランク(ハリー・トレッダウェイ)、レッド(ヘレナ・ボナハム=カーター)、ウィル(メイソン・クック。ローンレンジャーの格好をした少年)、シルバー
★ネタバレあり★
「ローン・レンジャー」は往年(1949〜57年)のテレビ西部劇シリーズ。元々はラジオドラマだったらしい。これまでにも何度か映画化されているようである。「ハイヨー、シルバー!」という馬への掛け声と、「インディアン嘘つかない。」という有名すぎるセリフの出どころである。トントが友を呼ぶ「キモサベ」という言葉も、なんとなく聞き覚えがある。
1869年のアメリカ西部。
東部で法律を学び郡検事となったジョン・リードは、列車で故郷の町コルビーに向かっていた。
列車には、町で絞首刑にされるため護送中の無法者ブッチ・キャベンディッシュも乗っていたが、仲間の列車襲撃により、脱走を図る。ジョンは、乗り合わせていたコマンチ族のトントとともに、暴走する機関車を止めるが、キャベンディッシュを逃してしまう。
町では、レンジャーのリーダ―であるジョンの兄ダンが追跡隊を組み、ジョンもそれに加わる。が、敵の待ち伏せに会い、隊は壊滅、ダンはキャベンディッシュに惨殺され、ジョンも瀕死の重傷を負う。通りすがったトントは、聖なる力でジョンを蘇らせる。兄の形見の服でつくったマスクをして「ローン・レンジャー」となったジョンは、トントとともにキャベンディッシュ一味を追う旅に出る。
白馬シルバーはスピリット・ホース(魂の馬)、トントは死者を蘇らせる悪霊ハンター、ジョンはスピリット・ウォーカー、キャベンディッシュは人の心臓を食らうウェンディゴ(悪霊)ということで、最近ありがちなホラーファンタジー風味の西部劇になっているのかと思ったが、実はそうでもない。
トントは、心に深い傷を負ったはぐれコマンチ、変な人っぽいが、あまりインディアンには見えない。ジョンは銃ではなく法による正義を貫くという、西部では腰ぬけと思われがちな信念を持ち、兄の妻となっているレベッカに昔と変わらぬ思いを寄せている。兄と弟のレベッカを巡る複雑な思いも描かれる。
といっても、軽快でコミカル、重たい設定なのに、だいぶのほほんとしている。
ジョンがローン・レンジャーと言えばこれという「ハイヨー、シルバー!」をやればトントが「二度とやるな。」といい、キモサベ(「信頼できる友人」の意らしい)の意味をジョンに訊かれると「出来の悪い弟という意味だ。」と答えるなど、ぴりっと笑わせる細部もある。
悪役は、インディアンでもエイリアンでもモンスターでもなく、強欲な白人であるのが潔い。
銃撃もあるが、見どころは列車のアクション。冒頭の悪党脱走劇もさることながら、クライマックスで延々と続く2つの列車並走アクションが、楽しい。
映画を見ているというより、ショウやアトラクションといった方が合っているようにも思う。
導入とエンディングが、1933年、サンフランシスコの遊園地であることが、また作り物めいて見せる。
作中、モニュメント・ヴァレーの風景がふんだんに出てきて目を楽しませてくれる。ラストのクレジットに重なって、赤茶けた岩に向かって延々と歩くトントの後ろ姿はよかった。(2013.8)
ジャンゴ 繋がれざる者 DJANGO UNCHAINED
2012年 アメリカ 165分
監督・脚本:クエンティン・タランティーノ
出演:ジャンゴ(ジェイミー・フォックス)、ドクター・キング・シュルツ(クリストフ・ヴァルツ)、ブルームヒルダ(ケリー・ワシントン)、カルビン・キャンディ(レオナルド・デカプリオ)、スティーブン(キャンディの執事。サミュエル・L・ジャクソン)、モギー(デニス・クリストファー)、ビリー・クラッシュ(ウォルトン・ゴギンズ)、ブッチ・プーチ/エース・スペック(ジェームズ・ラマー)、コーラ(ダナ・ミッチェル・ゴーリアー)、ララ(ローラ・カユーテ)、ダルタニヤン(アトー・エッサンドー)、ビッグ・ダディ(ドン・ジョンソン)、アメリゴ・ベセッピ(フランコ・ネロ)、サン・オブ・ガンファイター(ラス・タンブリン)、オールド・マン・カルカン(ブルース・ダーン)、鉱山会社の従業員の1人(クエンティン・タランティーノ)
★ネタバレあり!! 長いです
タランティーノの「ジャンゴ」である。
ちまたでは復讐劇と言われているが、というよりは奪還劇である。
ドイツ人のシュルツがジャンゴに話してきかせるジークフリートの物語そのままの、ヒーローがヒロインを救出する話となっている。
ジェイミー・フォックスがヒーローを演じて、実にかっこいい。
1858年、南北戦争直前のアメリカ南部。
黒人奴隷のジャンゴは、奴隷市場で売られ、買い取り先に届けられる途中で、歯医者で賞金稼ぎのドイツ人ドクター・キング・シュルツにより自由の身となる。
シュルツは、お尋ね者のブリトル3兄弟を追っていたが、彼らの顔を確認するため、同じ農園で働いていた奴隷を捜していたのだった。
シュルツとジャンゴは3兄弟のいる農園に乗り込み、彼らをしとめる。シュルツはジャンゴが有能なことを知り、二人はコンビを組んで賞金稼ぎを続けることになる。
シュルツは、ジャンゴが生き別れた妻のブルームヒルダを探していることを知ると、彼女が売られていった農場を突き止め、農場主のキャンディを欺いて彼女を奪還する計略を立てる。
二人は、キャンディに会い、架空の取引を持ちかける。うまくいきそうに思われたが、狡猾な奴隷頭スティーブンにより、計略は暴かれてしまう。
シュルツがキャンディを撃ち殺し、キャンディの用心棒がシュルツを撃ち殺し、邸は血みどろの銃撃戦の舞台となる。ここぞとばかりに白人を撃ち殺しまくるジャンゴだったが、多勢に無勢でついにはとらわれの身となる。
が、地獄の鉱山へ送られる道中、ジャンゴは護送係の白人をだまして武器を奪い、ブルームヒルダを取り戻すため、再び農場に乗り込むのだった。
「用心棒」「荒野の用心棒」「続・荒野の用心棒」、最近では「スキヤキ・ウェスタン ジャンゴ」まで共通していた、対立する2つの悪の陣営を煽って共倒れさせるという「血の収穫」ネタは、完全に取り払われている。
棺桶もガトリング銃も出てこない。
「続・荒野の用心棒」の冒頭、ぬかるんだ泥道を棺桶を引きずって歩いてくるヒーロー登場のシーンはかなり強烈だったが、こちらのジャンゴは奴隷ゆえ足かせをはめられ、鎖をひきずって登場する。重いものを引きずって歩いているという点が共通するといえなくもない。
黒人の奴隷は馬に乗れない。常に徒歩だ。だから、ジャンゴが馬に乗って現れるとみんなが見る。騎乗するとだいぶ目の位置が高くなる。ジャンゴは、白人たちを見下ろす。
最後の殴り込みでは、鞍も手綱も取り払った裸馬(白馬)に乗っていく。
覆面を被った男たちによる襲撃のシーンがある。「続・荒野の用心棒」では赤い覆面で、襲うのは白人のジャンゴである。こっちは、白い覆面で黒人を襲うのでKKKの本来の活動っぽいが、南北戦争以前の話なので、彼らはKKKの前身であるらしい。覆面といわず「袋」(bag)と言い、「前が見えねえ」「邪魔だから今日はなしにしよう」「だめだ、かぶれ」と、袋に関わるぐだぐだとしたやりとりはタランティーノらしくて、可笑しい。
血しぶきが飛び散る銃撃シーンは、マカロニ・ウェスタン同様、苦手な人も多いようだが、「キル・ビル VOL.1」などと比べれば、おとなしめだと思う。
一番憎らしい敵であるキャンディ(デカプリオが嬉々として悪役を演じている)を倒したのは、シュルツが袖に隠し持っていた小さな銃で胸にぽつっと小さな穴が空くのみ。
これが、盛大な血しぶきへのきっかけとなる。
シュルツは、穏やかなインテリであると同時にかなり危ない奴でもある。ジャンゴがキャンディの言動に腹を立て撃鉄に手をかけては我慢するシーンが何度かあったあとで、我慢しきれなかったのはシュルツの方だというのが、かなりいい。
アクションシーンには当然力が入っているが、タランティーノは、言葉にもこだわる。
最初の方、ブリトル3兄弟の最後のひとりが逃げるのを見て、ドクがジャンゴに言う。(※以下の会話は、大体の内容で、正確な収録ではありません。)
「やつだと断定できるか?」
「わからない。」
「わからないだと?」
「『断定』の意味が。」
「確かかってことだ。」
「確かだ。」
こういうやりとり好きだ。
このやりとりで、シュルツは、ジャンゴが言葉や表現をよく知らないだけで、ものごとをきちんと見極めて判断できるやつだと認め、相棒としてつかえると思ったのだ。たぶん。
で、ジャンゴにいろいろと言葉を教える。ジャンゴの名の綴りがDJANGOで、Dは発音しない字(黙字)だということも教えたのだろう。「D?」「このDは発音しないんだ。」「なんでだ?」「そういう字なんだ。」「じゃ、なんのためにあるんだ!?」てな会話が交わされたんだろうなということが容易に想像がつく。だから、彼は名前のスペルを聞かれると、一字一字答えたあとで「Dは発音しない」と得意げに付け足すのだ。
シュルツの遺体に向かって、“auf wiedersehen”(アウフ・ヴィーダーゼーエン)とドイツ語で別れを言うのもいい。その前に、シュルツがキャンディ(デカプリオ)に、「ドイツ語のさよなら(auf wiedersehen)は、また会うときまでという意味だが、おまえにはもう会いたくないから、グッド・バイと言おう。」と言っていたので、非常にわかりやすく泣ける。
フランコ・ネロ以外にも、ラス・タンブリンとかブルース・ダーンと言った名前がクレジットに出てくる。
パンフレットを読んだ人の話によれば、主役二人の馬の名前は、往年の西部劇スター、ウィリアム・S・ハートとトム・ミックスの愛馬の名だとか、手配書にエドウィン・S・ポーターの名が載ってたとか(罪状はもちろん列車強盗)、隠しネタがいろいろあるそうだ。
シュルツが、キャンディに対し、三銃士について語るところがあるが、これも二人の役者がともに三銃士の映画に出演経験があることと無関係ではあるまい。(デカプリオは「仮面の男」(1998)でルイ14世とその双子の兄弟フィリップ役を、ヴァルツは「三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船」(2011年)のリシュリュー枢機卿を演じている。)
知れば知ったで楽しいことがいろいろあるのだろうが、知らないなら知らないで全然いいように映画はできている。(2013.3)
このひと言(NO.58):「Dは発音しない。」
宿敵 因縁のハットフィールド&マッコイ HATFIELDS & MCCOYS
(ブルーレイ題名:ハットフィールド&マッコイ 実在した一族 vs 一族の物語)
2012 年 アメリカ テレビ・ミニ・シリーズ 105分×3話
監督: ケヴィン・レイノルズ
製作: ケヴィン・コスナー、 ダレル・フェッティ
脚本: テッド・マン
出演:“デビル”・アンス・ハットフィールド(ケヴィン・コスナー)、ジム・ヴァンス(トム・ベレンジャー)、レヴィシー・ハットフィールド(サラ・パリッシュ)、ジョンジー・ハットフィールド(マット・バー)、キャップ/ウィリアム・ハットフィールド(ボイド・ホルブルック)、グッド・ライアス・ハットフィールド(グレッグ・パトモア)、エリソン・ハットフィールド(ダミアン・オヘア)、コットントップ(ノエル・フィッシャー)、ウォール/ヴァレンタイン・ハットフィールド(アンスの兄。判事。パワーズ・ブース)、
ランドール・マッコイ(ビル・パクストン)、サリー・マッコイ(メア・ウィニンガム)、ロザンナ・マッコイ(リンゼイ・パルシファー)、ファーマー・マッコイ(マイケル・ジブソン)、トルバート・マッコイ(サム・リード)、ジム・マッコイ(トム・マッケイ)、バド・マッコイ(タイラー・ジャクソン)、カルヴィン・マッコイ(マックス・ディーコン)、ナンシー・マッコイ(ジェナ・マローン)
“バッド”・フランク・フィリップス(賞金稼ぎ。アンドリュー・ハワード)
ペリー・クライン(弁護士。ロナン・ヴィバート)
南北戦争後、アメリカで実際にあった2家族間の抗争を描く。
※ハットフィールド家とマッコイ家の争いは、主に1878年から1891年まで、アメリカ合衆国ウェストバージニア州とケンタッキー州にそれぞれ川を隔てて住んでいた、ハットフィールド家とマッコイ家の間で起こった実際の抗争。転じて、一般に対峙する相手との激しい争いを表す、隠喩表現となった。 (ウィキペディアより)
“デビル”・アンスと呼ばれるハットフィールド家の家長と、州境をはさんだところに住むマッコイ家の家長ランドールは、南北戦争をともに戦った戦友同士だったが、アンスは途中で離脱して故郷に逃れ、終戦まで戦ったランドールは無事帰郷するも心に傷を負っていた。戦争中に逃亡したアンスを快く思わないランドールは、アンスの叔父ジム・ヴァンスが、ちょっとした諍いから自分の弟ハーモンを殺したことを知り、両家はいがみあうようになる。
そんな中、アンスの長男ジョンジーとランドールの長女ロザンナが恋に落ち、状況はより複雑になる。町のイベントの折、またも両家でちょっとした諍いが起こり、アンスの弟エリソンが仲裁に入るが、ランドールの3人の息子たちが彼を殺してしまう。怒ったアンスは、彼らを捕え、法に委ねることなく、自分達の手で彼らを処刑する。
「これで終わらせるつもりだった」というアンスだが、このことはランドールの憎しみをかきたて、彼は、弁護士のペインと凄腕賞金稼ぎのフランクを味方につけ、ケンタッキー州の判事に訴えて息子たちを勝手に処刑したアンス家の面々をお尋ね者として手配するよう法的手続きをとる。
抗争は、1888年の「グレープヴァインの戦い」と呼ばれる戦闘でピークを迎える。ハットフィールド家の者が何人も逮捕され、ランドールの娘を射殺したエリソンの息子コットントップが絞首刑にされる。戦いを終結させるため、アンスは、知的障害を持つ若者コットントップを生贄として捧げたのだった。
延々と続く殺し合いは、陰々滅滅として気が滅入る。
アンスは、やり手の実業家で、頭もよく、人望もあるが、やくざの親分なみに暴力的手段に訴えるやつである。これに対し、ランドールは一貫してどうにも分が悪く見える。二人とも、抗争の中心にいるのだが、全体にドラマの描き方がたんたんとしすぎていて、相手に対する燃えるような憎しみがいまひとつ伝わってこない。この事態はまずいとか、こんなこと望んでいなかったのにこうなってしまったとか、坂を転がるような強烈な悲劇的な展開というものも感じられない。なにかというとすぐ人を殺したがる男たちが馬鹿者どもに見え、感情移入しづらい。
めちゃくちゃならめちゃくちゃで徹底してくれればそれなりに面白く見られるのだが、殺そうとしておきながら逡巡したり、なかなか死ななかったり、リアルな分、余計見ていて気が滅入る。そういう意味では、ジム・ヴァンスと若い隻眼のキャップのコンビはあらくれぶりが一貫していた。が、一番わかりやすく潔かったのは、父ハーモンをヴァンスに殺され、ハットフィールド家への復讐に生きるナンシーだった。彼女とフランクのカップルは危ない感じでなかなかよかった。
法律家としてまっとうな道を説くアンスの兄ウォールの揺るがない信念と、若いジョンジーとロザンナの恋が救いと言えば救いだが、ウォールは自ら望んで収監され、ロザンナはジョンジーと別れて悲運のうちに短い生涯を終える。両家の争いを嫌うジョンジーはまともな神経を持ち合せている若者として描かれているが、軟派すぎていまいち説得力に欠ける。が、終わり近く、戦いに疲れてきつつも不穏な面持ちのアンスが、水辺でジョンジーの話に耳を傾けるところは悪くなかった。(2013.4)
ブラックソーン ブッチ・キャシディ 最期の決闘 BLACKTHORN
2011年 フランス、スペイン、アメリカ、ボリビア 98分
監督:マテオ・ヒル
出演:ジェームズ・ブラックホーン(サム・シェパード)、エドゥアルド・アポダカ(エドゥアルド・ノリエガ)、サンダンス(ポードリック・ディレーニー)、キャシディ(ニコライ・コスタ=ワルドー)、エッタ(ドミニク・マケリゴット)、マッキンレー元ピンカートン社探偵(スティーヴン・レイ)、ヤナ(マガリ・ソリエル)
※日本では、2011年11月に京都ヒストリカ国際映画祭においてデジタル上映されたのみ。今回、知人が開催した西部劇研究会でDVD上映をしてくれたので見る機会を得たのだが、英語字幕だったので、細かい内容は把握できていない。
「明日に向かって撃て!」に登場した西部のギャング、ブッチ・キャシディが、ボリビアで名前を変えて生きていたという話。
1928年、ボリビア。ジェームズ・ブラックソーンと名乗り、地元の女性ヤナと静かな生活を送っていたブッチは、かつての相棒サンダンス・キッドの恋人エッタ・プレイスの息子に会うため、アメリカに帰る決心をする。
その旅の途中でエドゥアルドという若者に出会う。彼は、炭鉱から金を奪って逃走している最中だった。ブラックソーンが失くした金をエドゥアルドの追手が手に入れたと聞き、彼はエドゥアルドと手を組むことにする。
途中、若い頃のブッチとサンダンスとエッタの様子が挿入される。やりたい放題の武勇伝、エッタと別れてボリビアに向かう2人、そして迎える1908年のボリビア軍との対決。
一方、現在におけるブラックソーンとエドゥアルドの道行きは、激しい銃撃を交えつつも、淡々と進む。かつてブッチらを追っていたピンカートン社の探偵マッキンレーがなかなかいい味を出している。やがて、追手の正体を知ったブラックソーンは、苦渋の決断を下すことになるのだった。
どうも最近の西部劇の傾向のひとつとして、物静かで、渋く、すかっとしない結末、というのがあるように思う。本作もそんな感じだった。味わい深いが、苦い。
ボリビアの塩湖ウユニ湖で繰り広げられる追跡劇が圧巻である。どこまでも続く真っ白な塩の原に、逃げる側と追う側の騎影だけが、浮かび上がる。自然の背景なのにシュールで、美しい。(2012.7)
関連作品:「明日に向かって撃て!」「新・明日に向って撃て!」
おまけ:ウユニ塩湖(スペイン語:Salar de Uyuni)は、ボリビア中央西部の高原地帯(アルティプラーノ)にある塩の大地。標高約3,700mにある南北約100km、東西約250km、面積約12,000キロ平方メートルの広大な塩の固まり。正しくは、塩湖ではなく、塩原。(ウィキペディアより)
トゥルー・グリット True Grit
2010年 アメリカ 110分
監督:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン
原作:チャールズ・ポーティス「トゥルー・グリット」(「勇気ある追跡」改題)
出演:マティ・ロス(ヘイリー・スタインフェルド/エリザベス・マーヴェル)、ルースター・コグバーン(ジェフ・ブリッジス)、ラビーフ(マット・デイモン)、トム・チェイニー(ジョシュ・ブローリン)、ラッキー・ネッド・ペッパー(バリー・ペッパー)、クインシー(ポール・レイ)、ムーン(ドーナル・グリーソン)、ヘイズ(ブライアン・ブラウン)、ハロルド(ブルース・グリーン)、熊男(エド・コービン)、コール・ヤンガー(ドン・ピール)
★ネタばれ多少あり★
ジョン・ウェインがアカデミー賞を受賞したことで知られる1969年の西部劇「勇気ある追跡」のリメイク。少女が父の復讐を果たす物語である。
牧場の使用人チェイニーに父親を殺された14歳の少女マティ・ロスは、彼を捕えるため、連邦保安官ルースター・コグバーンを自費で雇う。父親に牧場の経理を任されていたらしいマティは、ビジネスと法律に詳しく、口が達者で、大人相手に一歩も退くことなく、てきぱきと駆け引きを行う。コグバーンは、ベテランらしいが、老いて、飲んだくれている。テキサスレンジャーのラビーフが加わり、3人はチェイニーが合流した無法者ネッドの一味を追ってインディアン居留地に足を踏み入れて行く。
「父の仇をわたしは取る!」という、「ワンピース」のルフィばりに明確で強固なビジョンを持った少女マティ・ロスに、凄腕保安官も誇り高きテキサスレンジャーもそして観客もぐいぐいと引っ張られていく。
クライマックスの1対4の対決は、オリジナルでジョン・ウェインが見せた馬上で手綱銜えて片手にライフル片手に拳銃というのとはさすがに違い、ブリッジスは馬上で二丁拳銃だったが、旧作のシーンを彷彿とさせる見せ場であった。
敵方のリーダー、ネッドの印象もオリジナルに近いものがある。悪党ながら割と紳士的で言動に筋が通っているという、昔懐かしい西部劇の無法者のボスの雰囲気を漂わせている。「ノーカントリー」であれだけ不気味な殺し屋を登場させたコーエン兄弟であるだけに、このあたりに彼らのオリジナルに対する敬意がこめられているようにも感じた。
というふうに、コーエン兄弟らしい乾いたケレン味がちらほら見受けられるつつも、骨太でストレートな西部劇に仕上がっている。
やたらと高い木につるされた死体を下ろすため、マティがやたらと高い木に登るシーンがとてもいい(高い所と木登りがが好きだからかもしれないが)。
エピローグは、25年後。39歳になったマティが、ウエスタン・ショーのテントを訪れ、コール・ヤンガー(ジェシー・ジェームズ率いる銀行強盗団の一員だった実在の無法者。服役していたが赦免されショーの興業をしていた。)からコグバーンの死を告げられる。マティは、亡き父の後を継いで大変苦労して牧場をきりもりしてきたらしく、見るからにこわそうなおばさんになっていて、コールの隣にいたフランク・ジェームズ(ジェシー・ジェームズの兄)をクズよばわりして去っていく。小生意気とはいえ、お下げ髪の可憐な少女だったマティの変貌ぶりがちょっと悲しいが、このあたりのハードボイルドな展開はコーエン兄弟の味か。(2011.4)
<追記>
機会があってもう一度映画館で見た。
1回目では気がつかなかったことがあったので、ちょっとメモ程度に追記しておく。
・最初と最後に柩を送るカットが同じような感じで入る。最初は、マティの父フランク・ロスの遺体を運ぶため。そうして最後は、マティがコグバーンの遺体を引き取って家の近くに埋葬するため。
・死体を置き去りにするシーンがいくつかあるが、それらがマティの視点でのトラックバックで撮られている。最初は、小屋の前にクインシーやムーンたちの死体を置いて行くとき。埋葬しないことを気にしていたマティは、馬上から遠ざかる死体をずっと見ている。ラスト、コグバーンが蛇に噛まれたマティを運ぶとき、射殺したネッドたちの死体が横たわる中を馬で進んでいくが、このときも運ばれるマティの視点で死体が遠ざかっていく。そして最後は、コグバーンが撃ち殺した馬のリトルブラッキーの死体。なんだかんだ生意気なこと言っているが、死体を置き去りにすることに痛みを覚える少女の思いが表されていると同時に、見送ることが彼女の追悼の気持ちを表しているのではないかと思ったりもした。(2011.4)