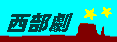
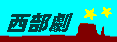
<作家姓あいうえお順>
<マニータとトム・ストーンとサグワロのシリーズ>アリゾナ無宿、 逆襲の地平線、 果てしなき追跡、 墓石の伝説(逢坂剛)
GREEN BLOOD(柿崎正澄)
シスターズ・ブラザーズ(パトリック・デウィット)
ワイオミングの惨劇(トレヴェニアン)
<ヴァージル・コールとエヴェレット・ヒッチのシリーズ>アパルーサの決闘、 レゾリュージョンの対決、 ブリムストーンの激突(ロバート・B・パーカー)
トゥルー・グリット(チャールズ・ポーティス)
時をこえる風 「囮たちの掟」所収(フ レデリック・フォーサイス)
荒野のホームズ(スティーヴ・ホッケンスミス)
此よりは荒野(水無神智宏)
オンブレ 3時10分発、ユマ行き(エルモア・レナード)
<マニータとトム・ストーンとサグワロのシリーズ>
アリゾナ無宿 The Arizonians
逢坂剛著
新潮社(2002年)
登場人物:ジェニファー・チペンディル[マニータ](17歳の少女)、トム・B・ストーン(流れ者の賞金稼ぎ)、サグワロ(記憶喪失の日本人、刀の使い
手)
日本人作家による西部小説。
小説新潮で連載が始まって第1章を読んだときは、幾分暗い雰囲気のハードボイルド風ウェスタンという印象を持ったのだが、単行本で全部を読んでみると、明るいトーンの楽しい作品だった。
物語の語り手でもある ヒロインのジェニファー(愛称マニータ)は、南部ゲリラに家族を殺され、インディアンと暮らしたあと、お尋ね者の男に引き取られるという辛い生い立ちにも関わらず、陽気で心正しい少女だ。彼女とストーンとサグワロで、バランスのよいチームになっている。
舞台は、1875年のアリゾナ州。 インターネットも携帯電話もない不便な時代で、彼らは、のびのびとやんちゃに活躍する。
インディアンは、部族によって言葉は違っても共通の手話があって、意志の疎通ができるらしい。常々、なんとなく手話っぽいものを使っているなあとは思っていたのだが、ちょっと目からウロコの気分だった。ジェシー・ジェームズが顔を見せてくれるのもうれしい。
小説新潮で第二弾が連載開始されているので、続きが楽しみです。(2003.2)
逆襲の地平線
逢坂剛著
新潮社(2005年)
アメリカ西部を舞台に、インディアンの手話がつかえる17歳の少女ジェニファー、賞金稼ぎの流れ者トム・B・ストーン、記憶喪失の侍サグワロが活躍する。「アリゾナ無宿」の続編。
今回、彼らは、二挺拳銃の若者ジャスティを新たな仲間に加え、女牧場主エドナの依頼で人捜しの旅に出る。
エドナの娘エミリは10年前にコマンチに連れ去られ消息不明になっていたのだが、最近になってコマンチのゲリラ部隊にエミリと同じ年頃の白人の娘がいたという情報を得たのだ。(この設定はどうしても映画「捜索者」を思い出させる。)
折しも時は1876年。白人は、インディアンから土地を奪い、彼らを居留地に押し込もうとしていた。理不尽な仕打ちに業を煮やしたスー族とシャイアン族は、北部に集結しつつあった。こうした事態はやがてモンタナ州リトルビッグホーンにおける第七騎兵隊の全滅という歴史的事件に発展し、さらに騎兵隊によるインディアン虐殺という悲劇へ続く。そうした状況を背景に、ジェニファーらはひたすら過酷な旅を続ける。
一行が追うコマンチのゲリラ部隊は、北上してスー族らとの合流を図っているらしいのだ。
途中インディアンとの遭遇や謎の襲撃者との銃撃戦、エミリ救出作戦など戦いの場面はいくつかあるが、基本的には旅の話である。先を行くサグワロが残していく目印を追い、砦や町に立ち寄っては情報を得るという地道な追跡行。
アリゾナから隣のニューメキシコに渡り、その後コロラド、ワイオミング、モンタナへと4つの州を行く。アリゾナ州の端から端までで日本を縦断するくらいの距離があるというのだから、この行程を馬や馬車で行くのはおそろしく難儀なことであるに違いない。
が、題名にもある「地平線」は、私にとっては昔からの憧れである。私が西部劇を好きになった大きな理由の1つだとも言える。(17、8年前アリゾナを訪れ、四方を地平線に囲まれたときの感動は今でも忘れられない。)と言うわけで、実際に旅したら本当に大変だと思うのだが、一行が荒野を行く様子を読むのは楽しかった。(2005.10)
果てしなき追跡
逢坂剛著(2017年)
中央公論社
幕末と西部開拓時代はシンクロするので、コラボする作品はけっこうある。映画では、「レッド・サン」「WEST MEETS WEST」は侍がアメリカ西部に行く話だが、「ラスト・サムライ」は第七騎兵隊のインディアン虐殺に加わってトラウマを負った騎兵隊の兵士が幕末の日本に来る話だった。
さて、本作は、同じ著者による西部小説「アリゾナ無宿」「逆襲の地平線」の前段となる話。2つの西部小説の主人公は少女とガンマンと謎の侍。その侍がどのようにして、西部にやってきたのか、というのが本作である。
1869年、函館、五稜郭。決戦に挑もうとした新選組副長土方歳三は、新政府軍の攻撃によって被弾し、重体に陥る。新選組の時枝新一郎とその妹ゆらが彼を救い出す。時枝は、土方とゆらをアメリカへ密航させる。サンフランシスコに向かう船上で意識を取り戻した土方は、しかし、記憶を失っていたのだった。船旅において、土方とゆらは、船長のケイン、看護師のクレア、黒人給仕のピンキーらと懇意になるが、一方、ちょっとしたいざこざから保安責任者ティルマンの恨みを買うこととなる。
アメリカに着いた土方は、ハヤトと名乗り、記憶が戻らないまま、ピンキーとともに西部へ向かう。サンフランシスコにとどまっていたゆらも二人の後を追うことに。保安官となったティルマンが、密入国者のハヤトとゆらを執拗に追ってくるのをかわしつつ、ゆらは、西部の町から町へと、愛する土方を探し求めてさすらう。
ハヤトが、インディアンのみんなの前で、日本刀で巨大サボテンをぶった切るところがよかった。
土方の含み針は、著者が拳銃に対抗するための武器は何かと考えてひねり出したと言っていたが、やはりどうもぴんと来なかった。
西部の町から町へのゆらの旅は、なかなか切なくてよかった。(2017.3)
墓石の伝説
逢坂剛著(2004年) 講談社文庫
西部劇蘊蓄小説とでも言えばよいのだろうか。歴史ミステリの楽しみも味わえ、西部劇ファンには実に興味深い一冊である。
西部劇の製作を試みる日本人のベテラン監督塚山新次郎と、映画評論家で西部開拓史研究家の神林小太郎、そしてコーディネーターの「私」こと岡坂神策との3人が、西部劇あるいは、西部開拓時代についてひたすら語る。
この三人に、塚山のドキュメント番組を製作するテレビ局のディレクター鷹島りおな、映画評論家で拳銃好きの葛城彰彦、塚山の姪の唐沢薫子、新人俳優の武者大輔、ガンプレイショーで活躍するアメリカのガン・ウーマン(?)アリゾナ・パティなどが加わり、蘊蓄の合間に、それぞれの出会いや、ポスターやパンフレットのコレクションの話や、ガンプレイショーの早撃ち競技の様子や、不法行為の疑いのあるガンマニアを尾行する刑事とのやりとりや、大手広告会社が西部劇映画製作に一役買うという夢のようなビジネス話や、男女関係の進展などが描かれる。
が、主眼はあくまでも西部劇。「シェーン」の黒い犬の話などもファンにはおもしろいものであるが、話題はやがて保安官ワイアット・アープと1881年にアリゾナ州のトゥムストンで実際にあったOK牧場の決闘に集中していく。(アメリカでは、ワイアット・アープに関して2冊の対照的な本が発行されている。一つは、スチュアート・レイクがアープ本人から聞いた話をもとに書いた「ワイアット・アープ伝」、もう一つは、フランク・ウォーターズがアープの兄ヴァージルの未亡人アリーの回想をもとに書いた“トゥムストンのアープ兄弟”である。前者がアープを英雄視しているのに対し、後者はアープを批判しているもので、この本によってアメリカではアープの評判ががた落ちしたという。そうした現象に疑問と反発を感じたということで、その後日本で津神久三氏が「ワイアット・アープ伝」(1988年)を書いた。作中では何度もこの本を引き合いに出し、その質の高さ
を賞賛しているが、今ではなかなか手に入らない希少本らしい。)何回も映画化され、日本でも有名なOK牧場の決闘が、どのような経緯で、どのような状況で行われたのか、詳しく検証していて興味深い。
後半、一行は、映画のロケハンを兼ね、それぞれの思いを抱いて、「墓石の町」トゥムストンを訪れる。そこでは、決闘から長い時を経て、意外な真実が明かされることになるのだった。 (2009.4)
参考:OK牧場の決闘関連作品「荒野の決闘」「OK牧場の決闘」「墓石と決闘」「トゥームストーン」
「ワイアット・アープ」
シスターズ・ブラザーズ THE SISTERS BROTHERS
パトリック・デウィット著(2011年)
茂木健訳 東京創元社(2013年)
★もろにネタばれしてます。悲惨な場面についても言及しています。
1851年のアメリカ西部。殺し屋シスターズ・ブラザーズとして知られるチャーリーとイーライの兄弟は、ボスである「提督」の指令で、山師ハーマン・カーミット・ウォームを殺すため、オレゴン・シティからカリフォルニアまで、西部横断の旅に出る。
チャーリーは飲んだくれだが拳銃の腕がたつ、欲得勘定最優先の冷酷非情な殺し屋。語り手である弟のイーライはでいったん切れると見境がつかなくなるが、普段は心優しい巨漢の好漢である(ちなみに彼が西部劇ファンが先頃その死を惜しんだ名脇役、「続・夕陽のガンマン」で「醜い奴」を演じた俳優イーライ・ウォラックと同じ名を持つことは多分偶然ではないと思いたい)。
この二人も、彼らが道中出会う人たちもみんなどこか素っ頓狂でユニークである。
あらゆる稼業に手を出しては失敗を繰り返している歯医者、なぜかは知らないがでくわすといつも泣いている男、森の中の小屋に住むオカルトめいた老婆、サンフランシスコの町の虜となった鶏を抱えた裸足の山師、泥をとかした湯をコーヒーだと言って人に勧める山師などなど。通りすがりの町のボス、メイフィールドは罠にはめたシスターズ兄弟に逆に子分の猟師たちを殺され、身ぐるみはがれながらも、冷静沈着に兄弟と交渉をする。
二人はやがてサンフランシスコの町に到着する。物価のばか高さに閉口しながら、彼らは、提督が派遣した斥候役のモリスを宿泊先のホテルに尋ねるが、彼は提督を裏切り、ハーマンとともに砂金採りに出かけてしまっていた。モリスが残した日記から、二人は、ハーモンが砂金採りのための秘薬を発明したことを知る。その薬を川に撒くと、砂金がきらきらと光ってみえるようになり、採取がぐっと楽になるのだ。「光の川」を目指して、ハーマンとモリスは一獲千金の夢を追いかけ、やがてシスターズ兄弟も彼らに加わる。このハーマンがまた波瀾万丈の人生を歩んできた独特な男であり、一方、モリスは都会育ちのオシャレな紳士、二人の対照もおもしろい。
しかし、4人が大量の砂金を手にして大喜びしたのもつかの間、秘薬は恐ろしい劇薬だったため、ハーマンとモリスは薬の強烈な作用により体中が毒に侵されて(強い酸だったのではないかと思われる)凄惨な最期を迎える。兄のチャーリーも、命を落とすことはないが、利き腕の右手を失う。
このラストだけでなく、全編を通して、暴力と肉体的苦痛を表す描写が多い。イーライは、のっけから毒クモに足を刺され、虫歯をこじらせて痛い目に遭う。彼の馬タブは、熊に襲われて目を負傷し、手荒い治療で目玉をえぐり取られた末に、弱り果てて崖から落ちて死んでしまう。二人の母は暴力的な父によって腕をねじ曲げられ、母を助けようとしたチャーリーは実の父を撃ち殺した過去を持つ。
しかし、陰々滅々とした内容がてんこもりであるにも拘わらず、読後、いやなものを読んでしまったという不快感はあまりなく、いや、不快に感じる人もいると思うが、私はそうでなく、残るのは哀切の情ばかりだった。
それは、イーライの語り口のせいではないかと思われる。ハーマンは、イーライのことを「なかなかの詩人だ。」と言ったが、その通り、イーライのものの見方は、ハードボイルドでありながら、児童文学や青春小説に出てくる青少年の語り手のような多感さも持っている。イーライは、歯医者から歯ブラシをもらい、歯磨きの習慣を身につける。めったに風呂に入らず全身汚れにまみれて旅をしているであろう西部男が、歯磨きを覚えて口の中をさわやかにすることに喜びを見出す、このちぐはぐさがイーライの魅力である。メイフィールドの会計係の女性(名前はわからない)といい感じになって、朝、二人でぬかるみのある通りを手をつないで散歩するところなどは、とても詩的で初々しいし、幌馬車隊に置き去りにされた少年に砂金を分けてやって故郷に帰るよう促すところは読んでいてほっとする。が、反面、切れると手がつけられなくなる自分や人を殺しにいく段になると気分がやたら高揚する自分の性質を自覚しているし、提督と決着をつけに行く際も実に冷静である。
大衆娯楽小説だと思って手にしたのだが、読み始めてすぐ、これは文学じゃないかと思った。B級娯楽アクションの題材を扱った芸術作品というところで、映画で言うと、コーエン兄弟やタランティーノに共通するものを感じる。歴然と文学なのに、あまりインテリくさくない。けれん味もあるのに、いやみじゃない。不思議なテイストの作品だった。(2014.8)
ワイオミングの惨劇 Incident at Twenty-Mile
トレヴェニアン著(1998年 アメリカ)
雨沢泰訳 新潮文庫
登場人物:マシュー・ダブチェク(旧式の散弾銃を持った若者)、B・J・ストーン(貸し馬の老人、元教師)、クーツ(黒人の元拳銃使い、ストーンの相
棒)、ケイン(よろず屋を営むユダヤ系の老人)、ルース・リリアン(ケインの娘)、ディラニー(酒場兼娼館「旅人歓迎ホテル」の経営者、元賭博師)、コー
ルダー(退役軍人、「旅人歓迎ホテル」の給仕)、クィーニー(白人娼婦)、フレンチー(黒人娼婦、顔に大きな疵がある)、チンキー(中国人娼婦)、ビョー
クヴィスト夫妻(食堂の経営者、スウェーデン人)、カースティ(ビョークヴィストの娘)、オスカー(ビョークヴィストの息子)、マーフィ(風呂屋兼床
屋)、ヒバート(鉱山会社が雇った牧師)、リーダー(脱獄犯)、タイニー(脱獄犯)、ボビーちゃん(脱獄犯)、ドク(鉱山技師)
西部開拓時代末期の話なので、西部小説といっていいと思うの だが、内容は暗くて暴力的、ついでに今風の心の闇を扱った、なんともやりきれない思いにさせられる物語である。が、不思議な吸引力があって、ぐいぐいと話に引きずり込まれていく。
1898年のアメリカ、ワイオミング州。鉱山とその麓の中間に、「二十マイル」と呼ばれる小さな共同体のような町があった。
前半は、「二十マイル」にある日ふらっとやってきた若者マシューが町に馴染んでいく様子と、刑務所を脱獄した凶悪犯リーダーらの逃走の様子が描かれる。や
がて、町は、リーダー一味の手に落ち、タイトルにある事件へと発展していく。
中心となるのは、旧式の散弾銃を抱えた謎の若者マシュー・ダブチェク。気のいい働き者として町の人々に受け入れられていくのだが、彼の背後には常に不穏な空気が漂っている。凶悪犯リーダーとマシューとのやりとりは、緊迫感に満ちていてはらはらさせられる。
そしてなにより、徐々に個性を発揮してくる町の住人たちに驚かされる。さびれた田舎町で暮らす彼らは、別格扱いのヒロイン、ルース・リリアンを除けば、最初はほとんど生彩がなく人生を捨ててしまっているような者ばかりに見えたのだが、話が進むとともにやがて一人、また一人とその存在感を示し、個性を発揮し始める。次は一体誰が何をするんだという期待が、結末まで一気に読ませてしまうのだ。(2004.8)
<ヴァージル・コールとエヴェレット・ヒッチのシリーズ>
アパルーサの決闘 Appaloosa
ロバート・B・パーカー著(2005年)
山本博訳 ハヤカワ書房
登場人物:ヴァージル・コール、エヴェレット・ヒッチ、アリー・フレンチ、ケイティ・グッド、ブラッグ、リング・シェルトン、マッキー・シェルトン、ラッ
セル・シェルトン、ウェイットフィールド、ストリンガー軍保安官助手
名うてのガンマン、ヴァージル・ コールと相棒のエヴェレット・ヒッチが、ア パルーサの町で保安官とその助手となって、町を牛耳る牧場主に立ち向かう。
悪玉の逮捕。移送途中での襲撃。 荒 野で寝泊まりしての追跡。インディアンと の遭遇。激しい銃撃戦。正統派西部劇の典型のような話であるが、その合間に絡む、ヴァージルと、ホテルのピアノ弾きアリーとの恋が、ひねりをきかせる。初めて恋仲になった白人女アリーに夢中になるヴァージルは、アリーの尻軽さを知っても彼女から離れることができない。
エヴェレットは、ウェストポイン ト (アメリカ陸軍士官学校)の出で、本もよく読み、エイト・ゲージのショットガンを愛用している。一方、ヴァージルは、クラウゼヴィッツの戦争論をことあるごとに持ち出すが、会話の中で単語を間違えて使ったりする。15年来のつきあいである二人の関係がいい。
連邦保安官助手や、敵方に雇われたガンマンたちは、ものの道理をわきまえているし、エヴェレットのお気に入りの娼婦ケイティは気持ちの良い女性である。
エベレットの語り口と、男たちが交わす言葉が実にシンプルで味わい深い。間が効いていて、心地いい。
そしてなによりも、本来脇役である位置のエヴェレットが、実は主役であるのが、完全にツボだ。
アパルーサは、架空の町だが、巻末の東理夫の解説によれば、もともとは、ぶち柄の馬の種類の名前らしい。物語にも、何回となく、荒野にたむろするアパルーサの種馬と彼が率いる牝馬たちの群れの様子が描かれている。
エド・ハリス監督、ヴィゴ・モーテンセン主演で映画化が決まっているらしい。とても楽しみだが、日本で公開されるかどうか心配だ。(2007.12)
続編:「レゾリューションの対決」「ブリムストーンの激突」(この下に掲載)
映画化:「アパルーサの決闘」(2008年)
レゾリューションの対決 Resolution
ロバート・B・パーカー著(2008年)
山本博訳 ハヤカワ書房
登場人物:ヴァージル・コール(ガンマン。元アパルーサの保安官)、エヴェレット・ヒッチ(ガンマン。元アパルーサの保安官助手)、エイモス・ウォルフソ
ン(サルーンとホテルと雑貨屋の経営者)、イーモン・オマリー(銅山のオーナー)、フリッツ・スターク(伐採・製材所の経営者)、ボブ・レドモンド(入植
者)、ベス・レドモンド(ボブの妻)、ビリー(娼婦)、フランク・ローズ(ガンマン)、ケイトー・ティルソン(無口なガンマン)、ルージャック(探偵社社
長、退役将校)、スワン(ルージャックの助手)
凄腕ガンマン、ヴァージル・コールと相棒のエヴェレット・ヒッチが登場する西部小説「アパルーサ」の続編。
タイトル原題は、前作に引き続き、往年の西部劇映画を思わせる西部の町の名前。
恋人アリーをめぐってトラブルに陥りそうなヴァージルの先手を打って町のボ スを倒したエヴェレットは、一人アパルーサをあとにして、山間にあるレゾリューション(解決)という名の小さな町にやってくる。
町には、サロンやホテルや雑貨屋を経営するウォルフソン、銅山を経営する オマリー、伐採業と製材業を営むスタークという3人のリーダーがいた。町の近くの
入植地には、家族とともにやってきて家を建て農場を営もうとしている入植者たちの一団がいた。
エヴェレットは、ウォルフソンに雇われ、彼の持つサロン「ブラックフッ ト」の用心棒となる。エヴェレットが来てから店内での争いが減り、娼婦をはじめ、町の人たちはトラブルの相談にやってくるようになった。
やがて、ブラックフットの向かいのサロンをオマリーが買い取り、二人のガンマン、ケイトーとローズが 雇われた。
そこへ、ヴァージル・コールがエヴェレットを訪ねてきて、二組のガンマンは通りをはさんで対峙する。
町の二大陣営の対立と思いきや、町を牛耳るボス対入植者たちの対決へ、と 思ったらインディアンの襲撃に対して町の住民は一体となって立ち向かうことに、と
思ったらやっぱり・・・というふうに対立の構図は二転三転し、敵となる軍団も入れ替わりが激しいが、主要な4人のガンマンは一貫して冷静である。
ヴァージ ル・コールはもとより、エヴェレットもローズもケイトーも強すぎで、あまりはらはらどきどきしないので、手に汗握るような緊迫感は感じられない。
かなり血なまぐさいことをしでかしているというのに、たんたんとした語り口は、やけに牧歌的だ。
ついさっき別れたばかりでも、何ヶ月も会わないでいた後の再会でも、二人 の男の間にかわされる言葉はそっけない。「エヴェレット」「ヴァージル」互いに名前を呼び合うだけの挨拶は2作目も変わらない。が、名うてのガンマンとその相棒だった二人の関係は、微妙に変化しつつあるようだ。(2008.12)
ブリムストーンの激突 Brimstone
ロバート・B・パーカー著(2009年)
山本博訳 ハヤカワ書房
凄腕ガンマン、ヴァージル・コール と相棒のエヴェレット・ヒッチのシリーズ3作目。
疾走したヴァージルの恋人アリーを追って、1年間旅を続けてきた二人は、リオ・グランデ川に近いうらぶれた町プラシドで娼婦に身を落としたアリーを発見し、店の用心棒を倒して彼女を連れ出す。
ヴァージルとエヴェレットは、ブリムストーンの町で保安官助手の仕事を得て、3人は1つの家に腰を落ち着けることに。
町では、もとギャングのボス、パイクが大きな酒場兼娼館を経営して羽振りを利かせる一方、兄弟愛教会(ザ・チャーチ・オブ・ブラザーフッド)の牧師ブラザー・パーシヴァルは、「戦闘的キリスト教徒」であるディーコン(執事)
らを率いて勢力を伸ばし、町に乱立するサロンを片っ端から排除していた。
パイクとパーシヴァルは裏で手を結んでいるように思えたが、やがてパーシヴァルは、パイクをも町から駆逐しようとし、二人は対立する。
町の二大陣営の対決というよくある話に、町の周辺で牛や人々を襲っては、死体に独特の矢を突き立てていく孤高のインディアン、バッファロー・カーフの話や、彼に襲撃され拉致され暴行された 母娘をヴァージルたちが保護する話が絡む。
前2作と同様、主役の二人はあいかわらずとても強いので、気張っている者もそうでない者も死ぬときは容赦なく死に、争いごとは、あっさりと型が付く。
アリーは、あいかわらずアリーで、 料理も歌もオルガンも下手だし誰とでもすぐ関係を持つし、後半ちょっといいとこを見せたということなのかもしれないが、おもしろみもだいぶ失われてしまって、どうにもうっとうしい女に見える。
チリカワ族とメキシコ人の混血であるポニーがしぶくてよい。彼は、パイクの手下だったが、インディアンを追跡するためヴァージルらに協力し行動をともにするうちに、やがて彼らの側につく。
心に大きな傷を負いながらも次第に心を開いていく少女ローレルもよく、主役の二人にくわえ、無口な登場人物がさらに二人加わったという感じである。 (2009.11)
このひと言(No.44):
「見合うぜ」俺が言った。「俺たちに」
「見合うな」ヴァージルが言った。
トゥルー・グリット True Grit
チャールズ・ポーティス著(1968年)
漆原敦子訳 ハヤカワ文庫
ジョン・ウェイン主演の西部劇「勇気ある追跡」(1969年)の原作小説。コーエン兄弟監督によるリメイク作品「トゥルー・グリット」(2010年)公開にあたり、改題して新訳で文庫版が出た。
西部劇は断然映画を見るのが好きで、西部小説というのは実はいまいち読む気にならない。広大な西部の風景や西部男独特のカジュアルないでたち、馬と銃の美しさといった視覚で楽しめる要素にくわえ、銃声と銃器を扱うときの金属音や、拍車の音、馬車や列車が走る音、そして音楽と、聴覚には少々鈍い私も、西部劇に出てくる様々な音が好きだ。
が、今回原作本を知人が貸してくれたので、読んでみた。「勇気ある追跡」はずいぶん前にテレビで見たきりで、「トゥルー・グリット」はつい最近映画館で見たばかり。そのせいか、出てくる描写にいちいちリメイク映画のイメージが重なる。元気で小生意気な少女マッティは長いお下げ髪のヘイリー・スタインフェルドだし、飲んだくれの凄腕保安官ルースターの言動もジェフ・ブリッジスのそれとして頭の中に浮かぶ。
話の筋や細部も映画は原作に忠実な部分が多く、本当は逆なのだが、映画のシーンをそのまま文章にしたような錯覚を覚える。言えば、テキサスレンジャーのラブーフの扱いが原作の方が映画よりもましである。彼は映画のように途中で決裂することなく、マッティとコグバーンにずっと同行し、それなりの活躍をみせる。
小説は、大人になったマッティが当時を振り返って語るという形をとっている。(映画もところどころ彼女のナレーションが入るが、画面を見ていると、そうした視点は忘れがちである。)彼女の語り口は淡々として潔い。讃美歌や聖書からの引用、カトリック信者をあまりよく思わないなど信仰に関わる物言いや、民主党をけなし共和党を擁護する政治的見解は、私にはよくわからない部分があるが、全てはプロテスタントで共和党支持者という亡き父の影響をうけているものと思われる。公開死刑の場で絞首台に立った男が、自分は親にちゃんとしつけられなかったからこんなことになったとして、「すべての親が、子どもたちの進むべき道を教え込むことを、私は願い、祈っています」と演説し、マッティも子どものころの親の教育が大事だと語るところがある。また、復讐を果たした彼女が、蛇にかまれて片腕を失うという展開には宗教的な意味合いを感じる。
少女が西部の男二人を従えて親の復讐を果たすという痛快西部劇アクションというだけでなく、教育的・宗教的な要素が加えられているのが興味深く、そのあたりがアメリカで人気小説となっている要因なのかもしれないと思った。(2011.6)
荒野のホームズ HOLMES ON THE RANGE
スティーブ・ホッケンスミス著(2006年)
日暮雅通訳 ハヤカワ・ポケット・ミステリ(2008年)
★若干のネタバレあり★
「西部にいたら避けられないものが、二つある。砂ぼこりと死だ。」
という出だしから軽快な西部劇を思わせ、その期待を裏切らなかった。ホームズへのオマージュと西部劇の要素を巧みに盛り込んだミステリ。
1892年のモンタナ。
洪水や病気で大家族の殆どを失い、2人だけ生き残った赤毛のカウボーイの兄弟が、ホームズとワトスン役となって、牧場で起こった殺人事件の謎を追う。
オールド・レッドと呼ばれる兄のグスタフ・アムリングマイヤーは、無学で文盲だが頭はよく、「赤毛連盟」という小説を弟に読み聞かせてもらって以来、名探偵シャーロック・ホームズに心酔し、探偵になるべく、日々観察力と推理力を高める努力をしている。語り手であるビッグ・レッドと呼ばれる弟のオットーは、論理的思考はあまり得意でないが、兄弟で唯一学問を受けたことがあり、字が読めて一般教養を身につけている、大柄でおしゃべりで、自分からはあまり言わないが、銃の腕もなかなかのように見受けられる。
職にあぶれていた2人は、臨時雇いのカウボーイとしてバー・VR牧場にやってくる。カウボーイ頭のマクファースンら元からいるカウボーイたちと差別され、銃を取り上げられ、劣悪な条件の中で労働をさせられる。
ある雷雨の夜、支配人のパーキンズが牛たちに踏まれ、無惨な死を遂げる。その後イギリス貴族の一行が牧場にやってくる。牧場のオーナーであるバルモラル公爵、娘のレディ・クララ、資産家のエドワーズ、貴族の子息のブラックウェルとメイドのエミリーらである。それからしばらく後、屋外トイレの中で、元からいたカウボーイの一人、アルビノ(白子症)の黒人ブードローが死体となって発見される。皆は自殺として片付けようとするが、オールド・レッドは、いくつかの根拠を示して殺人だと宣言する。保安官が来るまでに彼が事件を解決できるか否かということで公爵とブラックウェルが賭けをし、ここに「荒野のホームズ」が誕生する。
牧場での儲けをめぐる騙しあいに、ギャンブル好きで横暴な公爵に対する恨み、偶然通りかかった脱獄囚などが絡み、謎解きも読み応えがあるが、なんといっても、赤毛の兄弟を初めとする登場人物それぞれが魅力的である。とりすました貴族達と荒くれカウボーイたちの対照も鮮やかだ。上流家庭の落ちこぼれとして西部においやられたらしい軟弱そうな青年貴族のブラックウェルは、度派手なカウボーイのコスチュームで射撃や投げ縄の練習をしてみんなに呆れられるが、オールド・レッドは彼に親切にしてやる。彼がアムリングマイヤー兄弟の味方となり、終わりの方ではちょっと逞しくなっているのがうれしい。コックやメイドや職にあぶれた黒人カウボーイなどの脇役もユニークでイキイキとしている。そしてビッグ・レッドがめろめろとなる美女レディ・クララはハードボイルド小説っぽい役回りを果たす。
ビッグ・レッドの語り口は、軽快でシンプル、時折、亡くした家族や唯一残った肉親であるオールド・レッドへの愛情を見せられてほろりとくる。侮辱されたオールド・レッドのため、イギリス王室についての一般教養を披露して上流階級の面々を驚かせるところは痛快である。
最後に屋敷の一室に一同集っての謎解きは本格推理のお約束だが、荒くれカウボーイたちが窓やドアの近くで何かあればすぐ拳銃に手をかけるぞとばかりに屹立しているあたりが、西部小説ならではで心憎いのであった。(2015.7)
オンブレ Hombre
エルモア・レナード著(1961年)
村上春樹訳 新潮文庫(2018年)
村上春樹翻訳による、エルモア・レナードの西部小説。ポール・ニューマン主演の西部劇映画「太陽の中の対決」(1967年)の原作である。ジョン・ラッセルという、アパッチに育てられた白人の男が、駅馬車を襲った無法者たちとどのように戦ったかが語られる。
駅馬車には、駅馬車会社の社長で御者を務めるメンデス、もと駅馬車会社の社員で語り手の青年アレン、金を横領して逃亡しようとしているインディアン管理官フェイヴァーとその妻、アパッチ(チリカワ族)に連れ去られ、1か月後に救出された17歳の少女マクラレン、乗客の1人を追い出して無理やり乗り込んできた男ブレイデン、そしてジョン・ラッセルが乗っている。(こうした設定は、映画「駅馬車」を思わせる。)
途中で、フェイバーの金を狙った無法者一味が襲撃してくる。ブレイデンはその仲間の1人なのであった。
レナードの小説は、以前「ラブラバ」「スティック」「グリッツ」「野獣の町」を読んだが、あまり好みではなく、また、女性の扱いがけっこうひどかったような印象がある。「野獣の町」では鼻持ちならない女が出てきたがここまでひどい目にあわされなくてもと思った記憶があるし、「スティック」では、主人公のスティックが一晩のうちに次々に女性とベッドを共にしていくのが痛快そうに書かれていたがなんだか女をバカにしているように見えたし、ラブラバも具体的なことは覚えていないがあまりおもしろくなく、「グリッツ」に至ってはとても楽しみにして読んだのだが、そんなでもなかったことは覚えているが、内容を全く覚えていない。でも、新刊の文庫で西部小説が出ることなどめったにないので買って読んだ。
今回は、17歳の少女マクラレンがヒロイン的な役どころとなっているが、彼女がアパッチに凌辱されたことを駅馬車の乗客らはあけすけに話題にし、さらし者のようにされる。彼女は毅然とした態度でみんなに接し、ラッセルに対しても物おじせずにいて、言うことも正道だが、その姿は却って痛々しい。また、あまりよくない女に描かれていたファイバー夫人はひどい目に合わされる。
無口で粗野で銃の腕は立ち西部での生き方を心得ていて、「オンブレ」(スペイン語で「男」の意)と呼ばれるラッセルの言動は、アレンにより文字通り男の中の男、終始英雄のように語られる。しかし、英雄譚が語られるということは、つまりその男はすでにこの世にいないということ。最後はあっけなく、私としては、ヒーローには生きていてほしい気がする。
いま、レナードの西部小説が翻訳され文庫で読めるのも、ひとえに村上春樹訳のおかげなのだろうが、でも、やはりレナードはちょっと苦手だと思った。(2018.5)
3時10分発、ユマ行き Three-Ten to Yuma
エルモア・レナード著(1953年)
村上春樹訳 新潮文庫(2018年)
「オンブレ」の文庫に併載されていた短編。往年の西部劇映画の傑作「決断の3時10分」(1957年)、そのリメイク版「3時10分、決断のとき」(2007年)の原作である。以前、ミステリマガジンに掲載された高橋千尋氏の訳で読んだことがある。
ビスビーという町で駅馬車強盗団のボス、ジム・キッドが捉えられる。彼をユマの刑務所に送るため、保安官補のポール・スキャレンは、鉄道の駅のある町コンテンションまで彼を護送していき、ユマ行きの汽車に乗せなければならない。スキャレンは、妻子を養うために致し方なく安い給料で危険な仕事を引き受けている。銃の腕がたち、度胸もあるまっとうな心の持ち主である。コンテンションでは、ジムの部下たちがボスを奪還しようと待ち構えている。スキャナンは、彼らの攻撃をかわしながら駅へ向かい、ジムを連れて汽車に乗らなければならない。
映画はどちらもビスビーからコンテンションまでの二人の旅が割と長く描かれるが、原作では、二人はすでにコンテンションの町に着いていて、ホテルの一室に入るところから始まる。映画では、二人のやりとりによって、二人の間に、特にジムの方に芽生えてくる相手への敬意や共感の念が描かれていて興味深かったのだが、小説ではそれはさほどはっきりとは描かれていない。(2018.5)